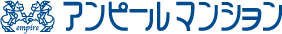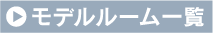chapter35 福岡県内にある日本一を探ろう!…その5 三種の日本一がある神社
シリーズで福岡県内にある日本一を探っている『知ってた?福岡』。
今回の日本一は、宮地嶽神社の紹介です。宮地嶽神社は、福岡県福津市にあり、創建約1600年といわれる有名な神社です。なんとここには、「日本一のモ ノ」3つもがあるんです。日本一のものが1つあるだけでもすごいことなのに3つもあるなんて!
…宮地嶽神社にある3つもの「日本一のモノ」とは何でしょう?
そこで今回は
~ 三種の日本一がある神社 ~
と題して、宮地嶽神社の3つの日本一をご紹介します。
日本一その1・大注連縄
宮地嶽神社にある日本一のもので最も有名なのは「大注連縄」です。この大注連縄、長さ13.5メートル、重さは約5トン、直径は最大部分で2.5メートルという巨大なものなんです。
神社の境内に入ると、ずっしりと重たそうな大注連縄が拝殿に掲げられています。拝殿の柱と比べてみると、明らかに注連縄と注連縄の房のほうが太いです。参拝のために大注連縄の下へ立つと、その縄の太さ、迫力に圧倒され、あんぐりと見上げてしまいます。
この大注連縄は、3年に一度架け替えをするそうです。
あらかじめ2反分の藁(小型トラック4台分)を使い、氏子さんを中心に藁を1ヶ月程を費やして縄 状に練り上げておき、12月の御神事の日に2本の大縄を大注連縄により上げます。御神事では、最大部分で直径約1.2mもある縄を1回よるたびにクサビを 打ち込んで、解けないようにして、大注連縄によりあげられます。よりあがった大注連縄は子供たちや参拝客が触れてみたり、藁の間に硬貨を差し込んだりし て、賑やかに縁起を担ぎます。その後、大注連縄はフォークリフトで拝殿の軒下まで持ち上げられ、縄でしっかりと取り付けられます。
実は、今年(平成20年)はその大注連縄の架け替えの年で、12月13日(土)に10時から架け 替えの御神事を行います。日本一の大注連縄の架け替えなんて、なかなか見ることができないことなので、ぜひ足を運びたいですね。勇壮な神事を見るとなんだ かご利益もありそうです。
日本一その2・大太鼓
宮地嶽神社にある2つめの日本一は、直径2.2メートルの大太鼓です。
今日ではこの太鼓より大きな太鼓はありますが、宮地嶽神社の太鼓は全て国内より調達した材料により製作され、特に国産和牛の皮をなめして作った左右の鼓面は、現在ではもはや同じものを作ることはできない大きさなのだそうです。
太鼓の胴部分はヒノキで、その表面に漆を幾度も重ね塗っています。これは音の響きを良くするためだといわれています。
普段は飾られているこの太鼓ですが、一体どんな音がするのでしょう?
この太鼓の音を聞くチャンスは1年に一度だけなのです。毎年、1月1日午前零時になったときに打 ち鳴らされるそうです。大きさからいって、かなりズウンと低く体中に響く音がなりそうです。初詣に宮地嶽神社へお参りして、この太鼓の音を聞くと1年の運 気も上がるかもしれません。
日本一その3・大鈴
宮地嶽神社にある3つ目の日本一は、大鈴です。
鈴というと、小さくてチリリンと鳴るものから神社の拝殿に掲げられている鈴までいろんな大きさのものをよく目にしますが、ここの大鈴は想像を超えています。なんと高さ3.0m、胴径1.8m、重さが450kgもある銅製の鈴なのです。
この鈴は、もともと大注連縄とともに拝殿に飾られていたそうですが、その重さのために鈴堂が別に建てられ、そこで奉安しています。鈴堂を見るとケタ外れの大きさでどーんと鎮座する大鈴に驚かざるを得ません。
日本一のもの3つが一堂に会する場というのはなかなかないことなので、一度はこの宮地嶽神社の三種の日本一を見ておきたいですね。
 福津市にある宮地嶽神社。福岡県内でも多くの参拝客が訪れる有名な神社です。
福津市にある宮地嶽神社。福岡県内でも多くの参拝客が訪れる有名な神社です。
 日本一大きい大注連縄。拝殿の柱と大注連縄の太さを比べると、その大きさ、太さを実感できます。3年に一度架け替えられます。
日本一大きい大注連縄。拝殿の柱と大注連縄の太さを比べると、その大きさ、太さを実感できます。3年に一度架け替えられます。
 日本一大きい大太鼓。これほどの大きさの国産和牛の皮をなめした鼓面は、もはや生産不可能だそうです。年に一度、正月元旦零時にこの太鼓が打ち鳴らされます。
日本一大きい大太鼓。これほどの大きさの国産和牛の皮をなめした鼓面は、もはや生産不可能だそうです。年に一度、正月元旦零時にこの太鼓が打ち鳴らされます。
 日本一の大鈴。重さは450kg!鈴という常識をはるかに超える大きさ。
日本一の大鈴。重さは450kg!鈴という常識をはるかに超える大きさ。
〔更新日:2011年11月01日〕